欲望の行く末
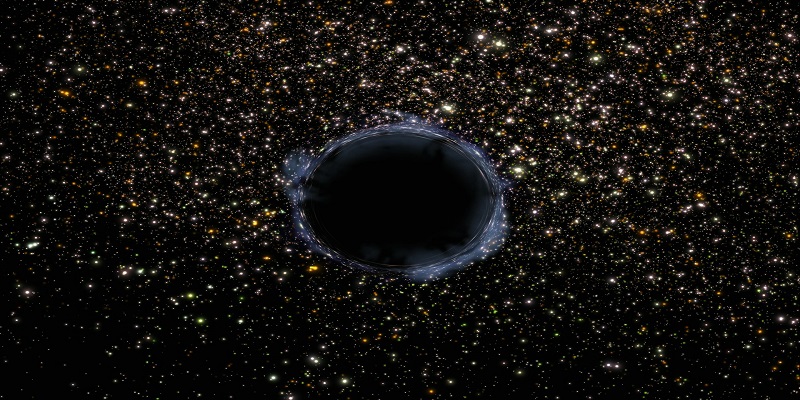
不規則に回る水車の音が響く。強弱ある動きは、それを回す力に強弱が生じているからだ。急激に魔力を弱め、このままでは町を守る巨大水車は止まってしまうと、今は町で唯一の魔物であるアンクルホーンのネロが、その巨体を生かして手で水車をどうにか回し続けている。
魔界という世界は常に暗雲に覆われ、地上世界における夜の景色の中に在る。その中において一つだけある人間たちの暮らす町ジャハンナでは、誰もが町の結界がみるみる弱まっているのをその身に感じていた。元は魔物だった者たちだ。町を守る結界の持つ聖なる気に対しての感覚は、人間に生まれた人間よりも鋭い。
巨大水車がのろのろと回るその裏手、町を守るように聳え立つ岩山の陰から、狂気を帯びたような魔物の光る目が見えた。町を守る水の流れは止まってはいないが、弱まる水の流れから生まれる聖なる気の力もまた弱々しい。通常ならば、いくら聖なる気が弱まっているとはいえ、魔界の魔物が好き好んでジャハンナの町へと入り込むような危険を冒さない。しかし現実に、岩山の陰には古くから魔界に生きるバズズの姿が見えている。猿の姿をしたバズズにとって、岩山に上ること自体は苦も無くこなせることだろう。たとえ登れずとも、その背には翼もある。魔物の目は、ジャハンナに住む元魔物である人間の姿を見る前から、赤く狂気を帯びた目を見せており、町を守る聖なる水の気配が一切なければ、何の迷いもなく既にジャハンナの町へと侵入していたに違いなかった。
けたたましい叫び声を上げて、三体のバズズが揃ってジャハンナの町へ足を踏み入れてきた。魔物が足を踏み入れてきた場所には、その獲物となる人間たちがいた。しかしジャハンナの町の武器屋サイモンと防具屋ブルートは、各々武器を手に魔物との戦いに臨む姿勢を見せていた。その姿は人間でありながらも、彼らの元の姿である彷徨う鎧、ソルジャーブルという魂を見せている。非力な人間となりながらも、彼らは決して戦い方を忘れてしまったわけではない。人間の姿になりながらも常に武器も防具も手に取り、この魔界という危険極まりない世界に存在するジャハンナの町の危機をいつでも頭の片隅に想像していた。狂気を帯びるバズズが直線的に向かってくるのを惹きつけるようにして、サイモンもブルートも、マーサが遺してくれたこの町を守るために戦う。
岩山の頂上の向こう、魔の世界を自由に飛び回る巨大鳥の姿が見えた。町を守る結界の弱いところを探すように、煉獄鳥が二匹、赤い炎を宙に吐いている。アンクルホーンのネロが諦めずに巨大水車を回し続ける限りは、町の結界が消えてなくなることはない。しかし安定しない守りの力は、敵につけ入る隙を与えるように、煉獄鳥の吐き出す炎が時折ジャハンナの町の中へと入り込む。
町の中へ敵をひきつける戦法に頼るわけにも行かないと、宙にある煉獄鳥に向けて鋭く矢が放たれた。キラーマシンのロビンが放った矢が、的確に敵の首元へと突き刺さり、一体の煉獄鳥はそのまま町の外へと落ちて行った。間を置かずにもう一矢、ロビンが左腕のボウガンから矢を放つと、残る一体もまた同様に町の外へと落ち、姿を消した。ロビンの赤い一つ目は決して爛々と狂気に光るのでもなく、しかしただの機械兵が放つような淡々とした光でもなく、この魔界の町を守らねばならないという己が責務のためにと、光を湛えている。人間と機械兵との約束があった。剣と矢を両手に構え、その約束を守ろうとするロビンには、既に機械を超えた意識がその身に宿っている。
空からの敵襲の姿は分かりやすく、その身に虹色の炎を纏う煉獄鳥は魔界の暗黒の空を色鮮やかに照らし、町へと近づいてくる。その数五匹。そして煉獄鳥の炎を目印するかのように、すぐ後からホークブリザードもまた五匹、姿を見せる。キラーマシンのロビンだけで対峙するには分が悪い。
ロビンと共に空を見上げる町の人の姿がある。普段は道具屋を営む元はミステリドールのお喋り好きミステル、人間となってもさほど容貌も変わらなかったと言われている元魔法使いのゆきのふ。魔物であった頃は一言も話すことのできなかった反動からか、人間の姿になった途端に話ができることに感動し、すっかり話すことが好きになったミステルだが、今は魔物の頃に戻ったかのように口を真一文字に引き結び、宙の敵を見据えている。様々な魔物という存在に精通し、宙から迫る敵に対しても落ち着いているゆきのふは、既に両手を前に構え、呪文の気配をその身に帯びている。
煉獄鳥の群れに向かって、ミステルの呪文が放たれる。ホークブリザードの群れに向かって、ゆきのふの呪文が放たれる。彼らに、直接敵と大いに戦う力はない。しかし戦い方には様々あるということが、宙にある敵の行動に証明される。
メダパニの呪文を受けた煉獄鳥の内三体が、同じくメダパニの呪文を受けたホークブリザードの内二体が、唐突に標的を変えるようにふらふらと宙に漂う。相反するような存在の魔物の群れは、混乱した中で互いを敵と見なしたようだ。煉獄鳥はホークブリザードに向かって激しい炎を吐き、剰えベギラゴンの呪文を放つ有様だった。対してホークブリザードは二体揃って凍える吹雪を吐き散らし、結果的に互いの弱点を突くような形で攻撃の応酬が始まった。メダパニの混乱を免れた他の魔物らも、その攻撃の巻き添えを食い、宙でぎゃあぎゃあとけたたましい鳥の声を上げる。手を緩めはしないと言うように、ミステルとゆきのふは追い打ちをかけるように、更にメダパニの混乱の中に敵の群れを放り込もうと、続けざまに呪文を放った。
一方で、ジャハンナの町の入口にはまだ人間になれないスライムのスラたろうと、元はスライムであった人間の子供の姿をしたスラきちが共にいた。町の不穏は、子供の姿をしたスラきちにも当然理解できている。しかし人間の子供という立場でできることは少なく、誘導する大人の指示に従い、町の中央に位置する避難場所とされた地下室へ向かおうとしていた。
その時、スライムの姿をしたスラたろうは町の入口の脇に現れた不穏な影を目にしてしまった。岩場を難なく上ることのできるバズズがここにも入り込もうとしていた。人間の子供の姿をしているスラきちは魔界の魔物の姿を見て足が竦み、その場に固まってしまう。ずっと傍で“友達”と言って遊んでくれていたスラきちを守らなくてはならないと本能的に思ったのは、まだスライムの姿をした自分もまた善いことをすれば人間に近づけるのだと信じていたからかもしれない。
バズズの目は真っ赤に染まり、明らかに常軌を逸していた。魔界の魔物は全てこれほどに凶悪なものなのかと、スラたろうもまたその場に震えたが、スライムの口を引き結ぶと、直後、「わぁっ!!」と敵を驚かすような大きな声を出した。と同時に、スライムの小さな身体が激しい光を放った。
その瞬間、自らが目を瞑っていたのだろう。目を開けた時には、目の前にいたはずのバズズの姿は消え去っていた。スラたろうが小さな身体全体から放ったニフラムの呪文の聖なる光が、悪しき魔物であるバズズの存在そのものを光の彼方へ消し去ってしまったのだ。
また何者かがこの場に現れるかも知れない。しかし人間の子供の姿であるスラきちと、小さなスライムに過ぎないスラたろうだけでこの場で勇敢にも、無謀にも敵を迎え撃つわけには行かないと、彼らは共に跳ねるように町の中央に位置する地下室へと駆けて行った。
ジャハンナの町は巨大な岩山のその上に位置するために、その地形自体が町を守っている。しかしその町を目指し、岩山の下に普段は見ないような魔物の群れがふらふらと現れて来る。それらは決して互いに意思の疎通を図るでもなく、協力して何かを成し遂げようとするでもなく、ただふらふらと姿を現わし、その目は狂気に満ちていながらも虚ろで、魔物自身の強い意思と言うものを感じない。ガメゴンロードにバザックス、そしてグレイトドラゴンと言った強力な魔物がはっきりと何かに操られるような動きで、ジャハンナの町を目指す。
ジャハンナの町を外で守るのは、ゴーレムたちだ。彼らはこの町の作り主でもある人間のマーサを慕い、元来のゴーレムの役目である使役される立場から、町を守る役を負う。突進してくるバザックスの攻撃にも耐え、そして町を守るゴーレムたちは敵とは異なり、互いに協力しながら町を守ろうと力を合わせる。攻撃に耐えるゴーレムの横から、別のゴーレムが大きな拳を振るってバザックスの棘のある固い甲羅ごと割り込む。ジャハンナの町の空に渦巻く暗雲から稲妻を呼び寄せるのはガメゴンロードだが、ゴーレムたちは稲妻に打たれ、身体が襤褸つこうとも、構わずガメゴンロードの甲羅へも拳を叩きつけようとする。アストロンの呪文で全く攻撃を受け付けない状態になれば、それを幸いとしてガメゴンロードを両手に持ち上げ、遠くへ投げてしまう。この魔物が回復呪文ベホマの使い手であることも、ゴーレムたちは知っている。自らが瞑想で身体の修復を行うゴーレムたちは、敵に回復手段を持たれることの煩わしさを重々に理解していた。
中でも強敵はグレイトドラゴンだ。身体の大きさも、ゴーレムたちとそう変わりなく、敵の数が多くなればゴーレムたちにも不利な戦いとなる。背に翼を持つために、宙を舞い、そのままジャハンナの町へと攻撃をしかねない黄金竜だが、その者自身の意思ではなく、行動を操られているからか動きは鈍く、直接翼をはためかせてジャハンナの町へと襲い掛かる気配は見せない。
敵が協力体制にないことを幸いとし、ゴーレムたちはこの巨大黄金竜に対して一体、一体と、集中して攻撃に当たった。ゴーレムたちの意識にあるのはただ一つ、人間たちが住むジャハンナの町を守り抜くことだけだ。無機物から作られた自身らは恐らく、マーサの力をもってしても人間の姿になることは叶わない。しかし善き人間になることを望んだ魔物たちが、この魔界の奥深くに存在するジャハンナの町でひっそりと暮らしているこの状況を、ゴーレムたちは決して壊したくはなかった。この町こそは、マーサの宝物なのだと、向かってくるグレイトドラゴンへと拳を振り、足で蹴り上げる。
グレイトドラゴンの吐き出す激しい炎の威力に、ゴーレムたちの身体も焼かれる。人間たちのように酷い火傷を負うわけではないが、炎を浴び続けてしまえば身体がボロボロと脆く、壊れてしまう。現に、ゴーレムたちの身体はところどころ大きく焦げ付き、その箇所を攻撃されては身体を支えきれないほどに削られてしまっていた。バランスを崩したゴーレムを守るように、他のゴーレムたちが集まるが、それでも徐々に劣勢へと追い込まれて行く。
その時、グレイトドラゴンの激しい炎を上方から打ち消すように、別の激しい炎が吐き散らされた。ゴーレムに向かっていた激しい炎は方向を変えられ、逆にゴーレムを攻撃しようとしていたグレイトドラゴンへと返される。
宙に飛んでいた別の巨大黄金竜が、他三体の同族と共に地面に降り立った。彼らの目に、何者かに操られたような虚ろの気配はない。寧ろ、己の意思を明確に持っているように見えた。先頭に立つグレイトドラゴンにおいては、その大きな角に濃紫色の布をはためかせ、己の為すべきことを今、目の前の状況に冷静に見つめている。
シーザーの雄叫びが響き渡ると、ドラゴ、トリシー、グレイトと言った彼の家族もまた、同様雄叫びを上げた。その声に、ジャハンナの町を守る役目を負うゴーレムたちは、彼らは敵ではなく味方なのだと悟る。シーザーたちが暴れる相手は、虚ろでありながらも凶悪な目つきを隠さない、魔界の悪しき魔物らだ。それが同族であっても、容赦することはできない。敵に回れば強烈に脅威であることを、シーザーたち自身が十分に理解している。故に、手加減することもできない。
グレイトドラゴンとグレイトドラゴンの激しい戦いが、ジャハンナの町を守る岩山の麓で始まった。シーザーの角になびく濃紫色の布は、彼だけではなく、彼の家族であるドラゴ、トリシー、グレイトにとっても、その意思を迷わせることなく導く。今、魔界に起きていること、魔界の空を常に覆う暗雲が、エビルマウンテンの頂上を中心に渦巻いている景色に、シーザーたちは意を決した。魔界に棲む魔物たちが己の意思など無く、ただ抗えない者に操られる如く動き出す光景を、魔界に生きる魔物たち自身が一匹とてその状況を望んでいないに違いない。己の意思もなく、単に破壊を始めることなど、生きているもの全てにおいて、望むわけもないことだ。
シーザーは同族においてもその強烈な尻尾を振り回し、叩きつけ、“目を覚ませ!”と吠えた。黄金に染まる巨大竜としての誇りがあるはずだと、ただ操られ動くのみの能無しに成り下がるなと、戦う。その父の姿を見て、娘トリシーも、息子グレイトも懸命に戦う。妻ドラゴもまた、夫シーザーの明確な意思に沿うように、宙に飛び上がり強烈な蹴りを繰り出す。四体のグレイトドラゴンたちが戦う間に、町を守るゴーレムたちは自身の身体の損傷を治すべく、瞑想に集中することができた。
この場で出会ったばかりのゴーレムとグレイトドラゴンだが、互いの意は同じところにあるとして、背中を預け合うように戦う。
敵の数が増える。明らかにこの町を目指して、どこからともなく湧いて出てくるように、魔物たちが姿を現わす。損傷を受けることが多くなれば、動きも鈍くなる。トリシーが翼を折られ、悲鳴と共にその場に蹲る。母ドラゴが庇い、同族へと激しい炎を吐き出すが、それもただの牽制に過ぎない。何せ、同族であるグレイトドラゴンに炎の攻撃はさほど効果がない。続けて攻撃を受け、ドラゴもまた腹に鋭い爪の攻撃を受け、その場に身体を丸める。
しかし次の瞬間、翼を折られていたはずのトリシーが、母ドラゴを守るために宙に飛んだ。そのまま宙がえりをするように身体を捻り、敵であるグレイトドラゴンへ母譲りの強烈な蹴りを食らわせた。翼の損傷が癒されていることに、トリシー自身が驚きのために目を瞬いている。
ゴーレムの肩に乗る人影がある。ジャハンナの町を出てきた二人が、ゴーレムたちの危機を救うために真剣な顔つきで状況を見つめている。元はネクロマンサーであった神父に、元ベホマスライムの宿の女将。二人は人間の姿となった時に、他の魔物と同様に魔物としての力をほとんど失ったはずだった。しかし命よりも大事なジャハンナの町の危機に、二人は失ったはずの魔物としての力をその身に再び宿していた。寧ろ、魔物であった頃よりも尚、その力は強いものとなって、彼らの手から発動される。それは偏に、彼らの強い意志によるものだ。
倒れたゴーレムに対し、神父は蘇生呪文ザオリクを発動する。傷つくグレイトドラゴンの家族に向かって、宿の女将が回復呪文ベホマラーを放つ。ゴーレムの肩に乗る二人は安定を保つために、敵の目から逃れるために、しがみつくように伏せながら状況を見守る。
思いがけない援けを得て、ゴーレムたちは、町の創造主であるマーサの意思を、遺志を守るべく、戦い続ける。グレイトドラゴンは竜としての誇りを持つのと併せ、受けた恩義を裏切るわけには行かないと、濃紫色の布を目の端に捉えるシーザーを筆頭に家族で戦い続ける。
エビルマウンテンの頂上、祈りの祭壇がある。その祭壇の上に、まるで祭壇の一部になったかのような巨像が立つ。
動きを止めたゴレムスの、宙に伸びる左の手の平は、頭上遥か高くに渦巻く暗雲へと向けられている。その手の平の上にはまだ、この世を去ったばかりのマーサの温度が残っているようでもあった。そしてそれは決してこの先も消えることはないと言うように、ゴレムスの手の平から上へと、暗雲をも突き抜けるように、青白い光が真っ直ぐに伸びている。
しかしその光は弱まっている。渦巻く暗雲が、まるで青白い聖なる光を巻き込み、取り込み、消してしまおうとしている。その悪しき力に乗じるように、エビルマウンテンに棲む煉獄鳥が暗雲に向かって伸びる光へと、激しい炎を吐きつける。光の持つ聖なる気配に、本来ならば悪しき魔物は好んで近づくことはない。しかし煉獄鳥の両目は赤く爛々と光り、到底正気を保っている様子などない。彼らもまた、他の魔物同様に、その行動は操られたものだった。聖なる光を恐れない。しかしそれ故に、知らず光の力に身体を焼かれ、煉獄鳥という炎を司るような魔物であるにも関わらず、その身を聖なる炎に包まれたままエビルマウンテンの山の谷へと落ちて行く者もいる。
煉獄鳥の群れに加え、ホークブリザードの群れも姿を現わす。一斉に光の柱が攻撃を受け、その力は徐々に弱まる。数が多い。敵の数が絶えることはない気配がある。このまま時を過ごせば、マーサの残した聖なる柱は魔の手に屈することになるだろう。
エビルマウンテンの頂上に立つ巨像は、ただの巨像になったわけではなかった。そこにはマーサの強く深い想いが残されている。友達のゴレムスは、その想いを受け取ると共に、この地に留まる覚悟を決め、そして最後の望みを託すように、マーサの子らを送り出した。
マーサの想いを無駄にしないという強烈な意志と共に、巨像となったゴレムスの身体から見えない力が溢れる。それが頭上に渦巻く暗雲と呼応し、暗雲は束の間、渦を巻き動くのを止めた。
瞬間、暗雲から幾筋もの稲妻が、エビルマウンテンの頂上目がけて落ちた。それは紛れもなく、ゴレムスの意志だった。マーサの想いを受け継ぎ、リュカたちに望みを託した、ゴレムスの切なる願いだ。ここで光を絶やしてはならないと、聖なる青白い光を守るために、ゴレムスは巨像となったその身においても、戦う力を顕わにしていた。
稲妻をその身体に受けた煉獄鳥もホークブリザードも、耐え切れなかったものたちはばらばらと谷へと落ちて行く。しかし元より魔界に棲むもの、それほど柔にはできていない。耐えた者らは変わらずこの煩わしい聖なる光を消し去ろうと、その元となるゴーレムの巨像へと襲い掛かる。動きを止めたゴレムスは、ただその攻撃に耐えるのみだ。
ズシン、ズシンと、祭壇の下で重々しい音が響く。新たな敵が現れるのが当然の場所でもある。このエビルマウンテンには別段、巨大鳥だけが棲みついているわけではない。それは足音、巨人族の足音が、祭壇の上を目指して上がって来る。
手にする棍棒は巨大極まりなく、その棍棒の攻撃に晒されたのは、ゴレムスを一方的に攻撃している煉獄鳥であり、ホークブリザードの群れだった。まるで虫を追い払うかの如く、巨大な棍棒を振り回し、ギガンテスが鳥の群れを蹴散らしていく。
ギーガは、巨人族が身に着ける粗末な服の懐に、白い花を忍ばせている。本心では、摘み取りたくはなかった。エビルマウンテンの麓、大魔王の居城の入口に立っていた彼は、頂上から伸びる聖なる光の弱くなった光景を目にし、初めてその場を離れる決意を固めた。土に根差して咲いている白い花の花びらが、急激に力を失ったように一枚、地に落ちたのを見た。彼は、マーサという一人の人間の女性が丁寧に世話をしていた白い花を、心の拠り所にしていた。このままではただ、白い花はこの場で朽ちてしまうに違いないと、彼はあの人間にこの花を託そうと、土ごと掘り返して摘み取った白い花の束を、根についた土もそのままに懐にしまっている。
エビルマウンテンの頂上の祭壇の上に、彼女の姿はなかった。その代わりに、見覚えのある、己とは異なる巨人の姿があった。しかしその者はただその場に立つのみで、動かず、しかし手の平からは青白い聖なる光が魔界の暗雲へと伸びている。その光に、ギーガは白い花と同じ、彼女のまとう空気を感じた。同時に、何かは分からぬままに、大きな一つ目から涙が零れた。
耳の聞こえないギーガの大きな一つ目に映る巨大鳥たち、そのものらはこの聖なる光を消し去ろうと暴れ回っている。魔界に棲む者として、ギーガも元来は、このような聖なる光など忌避すべきもののはずだった。しかし白い花を世話する人間の女性と出会い、大きな一つ目に映る白い花を心の拠り所とする内に、ギーガの中にある魔物としての邪悪はいつの間にかまるで落ち着いてしまっていたのだった。
ギーガの目が赤くなる。それは禍々しい者に操られているのではない。あの人間がいなくなったことに悲しむ、涙の一つ目だった。エビルマウンテンの頂上で、ギーガは生まれて初めて凄まじい雄叫びを上げた。周囲に飛び回る巨大鳥らが、轟音の衝撃に飛ぶことを止められたように、宙で均衡を崩す。ギーガは決して煉獄鳥やホークブリザードが憎くて、巨大な棍棒を振り上げているわけではない。動かなくなったゴレムスの姿に、ギーガは己のすべきことを教えられる。ただ暴れ回れば良いのではない。他のギガンテスに比べても大きな身体を持つギーガは、ゴレムスと意を同じにして、彼女の遺した最後の光を守らなくてはならないのだと、飛び回る巨大鳥を片っ端から棍棒で叩き払っていく。
魔界の奥深く、凄まじいエネルギーが放たれる中、リュカたちは戦いの舞台となる岩石の上で、身を伏せざるを得ない状況だった。少しでも気を抜けば、伏せる背中を抉られそうな圧に、ただ息を詰めて耐える。到底、その身だけでは耐えられないであろうビアンカとポピーを、アンクルが身を挺して守る。ティミーの身に着ける天空の防具は伊達ではなく、本来ならばまだ勇者としての使命を全うすることなどできない幼い身のティミーを守るべく、力を発揮して勇者を護る。プックルはその身に気合いを溜め、極力まで地に伏して宙からの圧に耐えている。ピエールは装備する風神の盾でその身を庇うように、身構えている。はぐりんはどこへ行ってしまったのか分からないと見せつつ、地面に薄い水溜りの如く平たくなり、大魔王の発する圧をやり過ごそうとしている。リュカはティミーの近くで、同じように地に伏せ、顔だけを辛うじて前へと向けていた。
その漆黒の瞳に映るのは、ミルドラースを大魔王と崇め、守ろうとしていた悪魔神官の姿だ。既に何体もの悪魔神官が、リュカたちとの戦いに敗れ、その姿を消した。そして今尚この場に残っている悪魔神官らもまた、主であるはずのミルドラースの手によって、その身を消されようとしている。
悪魔神官らは、あがいていた。声を発することもない者たちだが、宙に伸ばされる手が、何かの救いを求めていると言うことは、リュカにも分かった。しかし彼らが救われることもないことを、リュカも、彼らも、分かっていた。それでも足掻こうと、手を伸ばしもがくのは、偏に命に対する執着なのだろう。
悪魔神官らの足掻きも虚しく、悪魔の法衣を身に着けた彼らは一体、また一体と、宙に浮かびながら変貌を続けるミルドラースの身体へと取り込まれて行く。その光景を、リュカは僅かに顔を上げながら目にしていた。リュカにしては珍しく、救いたいとも思わなかった。邪悪に身を染め、悪魔を崇拝するような神官となった元は人間だったものたちが、戻れるような場所があるとは思えない。悪魔神官となってしまった者は、自ら戻る道を捨てたに等しいのではないだろうかと、次から次へ姿を消す悪魔神官を、リュカはほとんど無感情に見つめていた。
宙に飛んでいく悪魔神官の群れの中、ミルドラースの周りを浮遊していた岩石がいくつか宙に止まった。岩石は様々な形をしているが、ミルドラースの変貌が進むにつれて、それらは不穏な黒い影を纏い始めた。その一つを、リュカは辛うじて開けている目に見つめる。
黒い影の向こう側、岩石の表面には動く景色が見えた。それは日の当たる地上の世界。リュカ自身もその景色を、空から眺めたことがある。大森林の中に守られる国、グランバニア。大森林には今、暗い影が落ち、その暗い大森林の中に動く者たちが見える。
動きを止めた岩石には一つ一つ、地上世界の景色が映し出されている。その全てを、リュカは知っている。親友の国、砂漠の国、花々に彩られる町、母の故郷の村。その全てが今や影を纏い、闇に呑まれようとしているような景色を見せている。目の前で、変貌を遂げようとしているミルドラースの邪悪が、この場などには収まることなく、地上世界にまで及んでいることに、リュカは気づいた。
圧に耐え、リュカはその場に立ち上がろうとする。しかし同時にミルドラースの身体を作り上げる邪気が膨れ上がり、瞬間、再びリュカは地に伏せざるを得なかった。痩せた人間の老人を思わせる風貌だったはずのミルドラースの身体が、悪魔神官という僕を取り込んだことも手伝い、ぶくぶくと膨れ上がっていく。その姿は、ただただ醜悪と言わざるを得ない。しかしミルドラース自身はその醜悪さなどには気づかず、寧ろその表情には満足の笑みさえ浮かび始めている。
人間の姿は到に捨て、その身は赤黒く、黒のまだら模様を浮かび上がらせている。膨れ上がる巨大な身体は、ただぶくぶくと膨れ上がるだけで、それだけで醜悪という状態を表現している。膨れ上がるのは身体だけではなく、併せて欲望もまた膨れ上がり、醜悪な赤黒い身体の膨張は止まらない。
ミルドラースの周りに浮遊する岩石に映し出される景色は、まるで黒い煙に覆われるように見えなくなってしまった。歯噛みするリュカは、為す術もない状況を打破するためにも、左手に掴んでいるドラゴンの杖に強く念じる。まさに神頼みだと思いつつも、竜神もまたこの世界を滅ぼしたくはないはずだと、その力に望みを賭ける。しかしいつものこと、ドラゴンの杖の桃色の宝玉は素直に応えてくれるわけでもなく、このような状況においても大魔王の変貌を見届けようと、静観している。
地上世界にも危機が訪れているとすれば、竜神は決して怠けているのではなく、今は地上世界を守ることに尽力しているのかも知れないと、リュカは杖を握る手からふっと力を抜いた。
神頼みなど似合わないと、リュカは自分で自分のことをそう思う。マスタードラゴンと対面を果たした稀有な存在となりながらも、恐らくこの世で唯一のドラゴンの杖という竜神の魂宿る杖を託されようとも、リュカは決して何事をも神に頼むことなどしなかった。その点において、自分は誰よりも神から遠い存在なのではないかとさえ思う。己が本心から頼みにするのは、亡き父、亡き母の存在に他ならない。
その想いが今度は、リュカの右手にある母の命のリングに宿り、右手に掴む父の剣へと伝わる。一度は折れてしまった父の剣は、プックルやピエール、グランバニアの人々の想いの元に、再びの姿を見た。この剣はただの父の剣ではなく、皆の想いも宿り、そしてリュカの亡き父パパスへの想いも宿らせる剣だ。人の想いというのは、果てのない力を生み出すものだということは、リュカは己の命がここまで続いてきたことに実感している。どこで途切れてもおかしくはない命だった。しかしリュカは諦めなかった。それと言うのも、リュカを諦めなかった者たちがいたからだ。
ミルドラースの変化が止まない。不気味な音が聞こえ、吐き気さえ催すような音と共に、既に怪物の様相を呈したミルドラースの腕が生える。大魔王を自称する者は、腕が二本では足りないのか、更に二本の腕を生やし、それでもまだ変化を止めない。大魔王の発する圧力に抗おうとしているのは、リュカだけではない。勇者ティミーもまた、伏せながらも天空の剣の先を大魔王に向け、その意を表すことを止めない。息子もまた、岩石に表れていた地上世界の異変に気付いたに違いない。その横顔はまだ十歳の少年にはとても見えなかった。世界を救わねばならないと決意と覚悟を顕わにしている勇者そのものだ。
地面に押しつぶされそうな圧が、強まる。顔を上げていられず、リュカの持つ父の剣も、ティミーの持つ天空の剣も、地にへばりつく。プックルが堪らず雄叫びではなく悲鳴を上げる。圧に耐え切れなければ、身体ごと押しつぶされ、それだけで絶命しかねない。ビアンカとポピーを守るアンクルも上からの圧に耐え、守る二人を圧し潰してしまわないようにと、呻き声を上げながら必死の形相で耐えている。ピエールの緑スライムははぐりんに習うように極力平べったくなり、鎧兜を着込んだピエールは声を上げることもできず、死んでしまったかのように静かに耐えている。
宙に凄まじい風が起きた。顔を上げてそれを見ることも叶わない。轟音と共に吹き下ろされた風の原因は、ミルドラースを更なる怪物に変貌させた尻尾が振るわれたものだった。尾の先に巨大な棘が生えている。それはミルドラースがその身に吸収してしまった悪魔神官が手にしていた棘の棍棒を彷彿とさせた。敵となる者を倒すだけではなく、嬲り、痛めつける惨さを感じさせる一方で、それは誰一人周りに寄せつけたくないという、全てを拒絶する意思の表れでもあった。頼る者は、己のみ。周りの者は、誰一人信じることはできない。究極の孤独の中に大魔王はいる。
全てを払い除けるかのような風が吹き下ろされた。それはミルドラースを大魔王として完成させるために生えた、巨大且つ禍々しいばかりの翼が起こした暴風だった。その場に立っていたら耐えられなかったような暴風だった。そしてその暴風の後、辺りから強烈な圧は去った。身体が解放されたような感覚を得て、最も早くにその場に立ち上がったのはティミーだった。剣を握り、盾を構え、その場に飛び起きると、勇者ティミーは大魔王を宙に見据えた。
ぶくぶくと太り切った赤黒い身体にも、長い舌をだらりと垂れる締まりのない口にも、全身に浮き出る気味の悪い黒の斑にも、形ばかりでたるんだような巨大な翼にも、全てにおいて醜悪が滲み出ていた。ティミーは思わず顔をしかめる。一体この者は何を目指していたのだろうか。この姿が本当に自身のなりたい姿だったのだろうか。到底そうは思えない。
リュカもまた立ち上がり、ミルドラースの成れの果てとも言える姿を見上げる。つい先ほどまで、人間の老人の姿をしていた時にはまだ、勇者も神をも超えた存在だと自負する言葉を口にすることもできただろう。その言葉には、己がこの世界の、魔界も地上の世界も統べる者だという誇りにも似た意思を感じられた。しかしすべての醜悪を曝け出したような今の状態に、この者の誇りはもはや微塵も感じられない。ただただ己を認めなかった神、人々への復讐、何としてでも己の究極の存在を認めさせてやるのだという、拠り所のないただの執念。そのようなミルドラースの怨念のような思いは、ひたすらにその姿を醜悪なものへと変えてしまった。持て余しているような牙が口からはみ出し、閉じない口からは涎が垂れている。この者曰く、気の遠くなるような長い年月を経て己は神をも超えたとしていたが、その年月をかけて育て上げてきたのは、くだらない自尊心と嫉妬ばかりだった。リュカにはそうとしか捉えられなかった。
このようなくだらない自尊心の化け物に支配されることなど、人間も、魔物でさえも望んではいないに違いない。リュカは初めから、人間の味方をしているわけではない。恐らく世界の中でも魔物との交流を持つ珍しい人間の一人だ。現に今、意を同じくしてプックルが、ピエールが、アンクルが、はぐりんもまた、この危険極まりない場所に共に立っている。エビルマウンテンの頂上ではゴレムスが、大魔王の居城入り口にはギーガが、ジャハンナの町にはロビンや元は魔物であった人々、地上世界のグランバニアにはリュカたちの帰りを待つ人々も魔物の仲間たちもいる。それだけにも留まらない。リュカの出会っていない人々も魔物も、まだ数多世界に生きている。その全ての命に対して思いを寄せるのが、あらゆる者が望む“神”という存在なのではないだろうか。
それとは対極をなす思いを育んでしまったのが、このミルドラースという大魔王なのだろう。常にその目に映るのは、己のみ。まだ鏡に映る自身を見るのであれば救いはあったろう。しかしミルドラースの見る己自身というのは、単に己が想像する中での、完全無欠の姿を極めた自分自身だった。決して真実の己の姿に目を向けようとはしなかった。鏡に映るような自身の姿など、彼には不要だった。
そのようなくだらないと一蹴するべき存在に世界が滅ぼされては、誰一人浮かばれないであろうと、リュカは右手に父の剣、左手にドラゴンの杖を持ち、改めて醜悪な化け物となり果てたミルドラースを見据える。
アンクルの護りの中にあったポピーもまた、母ビアンカと共にその場に起き上がっていた。ビアンカはこのような場においても冷静だった。と言うよりも、彼女が本能に従ったまでの行動だった。握りしめていた賢者の石に祈りを捧げるその行動は、彼女の皆を想うという本能であり、マーサから託された賢者の石に込められた万人を救いたいという願いから生まれるものだった。ビアンカの母としての想いと、マーサの母としての想いは重なり合い、それは強い癒しの風となって皆に届く。
母の隣に立つポピーの目に映るのは、兄ティミーの堂々たる立ち姿だ。天空の剣を右手に、天空の盾を左手に、神々しい天空の鎧を身に纏い、今にも空に飛び立ちそうな両翼を備えた天空の兜を被る兄の姿は、まさしく大魔王と対峙する勇者の姿と見えた。勇者の兄を持ち、双子の妹に生まれた自分だが、己はあの姿をする運命には生まれなかった。しかしその心はいつでも、勇者の兄と共にあった。勇者に生まれ、素直に勇者となった兄を羨ましいと思う心はあれど、兄を妬む気持ちは生まれなかった。それは何故か。
兄ティミーがいつでもこちらを向いていてくれたからだ。妹ポピーを置き去りにすることなど、決してなかった。寧ろ、ポピーの力がなければならないのだというように、いつでもその手を取り、常に共に歩んできたために、ポピーは自身もまた勇者の一人なのだとその心に思いを刻んでいた。
己に天空の武器防具を身に着ける役割は与えられなかった。しかしその代わりに彼女が己の身に宿したのは、到底一人の少女がその身に備えることのできるようなものではない、強大な魔力だった。そしてそれは勇者の身において、竜神マスタードラゴンとも通ずるものがあるのだと、ポピーは父が扱うドラゴンの杖にそれを知っている。
リュカが手にするドラゴンの杖の宝玉が、杖の主となった人間の王の心と、もう一人の勇者として悪に立ち向かわんとする少女の心に触れ、激しく輝いた。隣で巨大な黄金竜と姿を変えて行くポピーの足にしがみつくビアンカは、娘が竜の姿に代わるや否や、尾に導かれるようにその背に乗った。そしてその尾はすぐに、兄ティミーの元へと誘われ、ティミーは一つ頷くとすぐにポピーの竜の背に乗り込んだ。
同時に姿を変えたのがリュカだ。ポピーよりも二回りも大きな黒竜へと姿を変え、その姿は目の前で変化を遂げたミルドラースに勝るとも劣らない恐ろしい顔つきを見せている。これまで、リュカが黒竜へと姿を変えた時には必ずと言ってよいほどに、リュカはひたすらに暴れまくっていた。唯一それを抑えることのできた妻ビアンカは今、娘ポピーの黄金竜の背に乗っている。それ故にアンクルはビアンカの元へと飛び出した。彼女がリュカの傍にいるべきだという、アンクルらしい冷静な判断だった。
しかしその必要はなかった。リュカは黒竜と姿を変えても尚、己の人間としての意思を明確に持ち続けていた。リュカは、目の前で醜悪な化け物と成り果てたミルドラースと言う、自らを大魔王などと称する者に、世界を明け渡してはならないと自らの意思に強く思った。彼がそう思えたのは、彼が決して一人で生きてはこなかったからだ。
亡き父、亡き母、家族、仲間たち、国の人々、各国の人々、旅の中で出会った人々。彼に於いては、人に限ったことでもない。多くの仲間たちの中には魔物もいる。人間の敵とされる魔物だからと言って、決して悪いばかりの者たちではなかったと、リュカは旅の中で知った。そのような者たち、人間も魔物も、このミルドラースの為そうとすることを快く受け入れることなどできないに違いない。誰も望まないような世界を生み出さないためにも、リュカは竜神の力を借りてでも、この者を滅ぼさなければならないと、己の中から情けと言うものを一切捨てた。
黒竜へと姿を変えたリュカの背に、プックルが、ピエールが駆け上がった。宙高くに浮かんでいるミルドラースに向かって、黒竜の漆黒の目が、プックルの青の目が、ピエールの兜の奥の目が向けられる。彼らの間において、互いの信頼関係には微塵の疑いもない。自らを王の中の王などと呼ばわり、膨張極まった身体の上に乗る醜悪な顔でリュカたちを見下ろすミルドラースへと、黒竜は大きくその翼をはためかせた。
閉じない口から、既に炎が漏れていた。ミルドラースの全てを飲み込んでしまうような大きな口から吐き出されたのは、灼熱の炎だ。魔界の闇の空間が、赤く明るく染まる。黒竜と黄金竜はそれぞれ反対側に、灼熱の炎が吐き出される方向を定めさせないよう飛び回る。しかしミルドラースの吐き出す灼熱の炎はそもそも方向など定めず、己の周囲全体を一気に炎で埋めるほどの勢いで飛び散って行く。たまらずリュカもポピーも竜の身体に頼るように、炎の勢いに耐え、背に乗せる者たちを庇うためにミルドラースを正面に見る。いくら竜の身体を持つとは言え、灼熱の炎を浴びて無傷ではいられないと、ティミーは妹の背で防御呪文フバーハを唱える。
直後、ミルドラースの巨体から凍てつく波動が放たれた。それも、灼熱の炎を吐き散らしながらだ。すかさず破られたフバーハの呪文の衣は、呆気なく空気の中に散ってしまった。しかしそれごときでティミーの心は一瞬たりとも挫けない。完全に人間の姿を捨て、異形の怪物と成り果てた赤黒い巨体が敵となったのだ。何が起こっても、想定内としなければならない。その中でも、世界を滅ぼされることだけは、想定内としてはならない。それだけが、ティミーのみならず、皆の頭の中にある。
黒竜の背後に隠れていたアンクルが飛び出し、デーモンスピアを片手に大魔王へと単身向かう。黄金竜の背の上に立つビアンカは、止んだ灼熱の炎の熱をも凌駕するようなメラゾーマの呪文を放とうと、マグマの杖を振り上げる。メラゾーマの呪文の空気に反応するように、杖頭のマグマが激しく沸き立つ。
その巨体故に、動きも鈍く見えるミルドラースだが、その鈍さは巨体で補われる。赤黒い鈍重な巨体が回転し、背に生やす翼を動かすだけで、周囲の者たちを跳ね除けてしまう。激しい突風に、アンクルは宙で止まらざるを得ない。寧ろやや押し返されてしまう。ポピーはその場に耐えた。その背に立つビアンカはメラゾーマの準備を終える。頭上に巨大火球を生み出す。彼女の呪文攻撃を止める者はいない。皆が、今のミルドラースに呪文防御の膜など張られていないと認めている。姿形を変える前、ミルドラースの身体にマホカンタの呪文を施していた悪魔神官らは、一体たりともこの場に残っていない。大魔王の巨体にもその攻撃は届くに違いないと、誰もがメラゾーマという大火球の威力を信じていた。
一瞬、ビアンカはメラゾーマを放つのを躊躇した。ミルドラースの真っ黒の目が、彼女に向いたからだった。怯んだと言えばそれまでだが、彼女は直感的に放てなかった。ミルドラースの膨れ上がった身体に取り込まれた、無数の悪魔神官の魂の声を聞いたような気がしたからだった。
彼女の直感は的中。ミルドラースの怪物の巨体に取り込まれた悪魔神官らは、このような状況にあっても尚、我が主を支えなくてはならないのだと、まるっきりの盲目状態で呪文を放ったのだ。ミルドラースの身体と一体となった悪魔神官にその意思があるのだとは感じられないが、現実に大魔王の巨体はマホカンタの呪文の護りを受けた。
ビアンカが放とうとしていたメラゾーマの大火球は、宙に馴染み、消えていく。その光景を見るミルドラースの目は、満足そうに歪む。そして一度、邪悪の翼をはためかせると、忌々し気に歪めた顔つきも隠さずに黄金竜ポピーへと向かってくる。大魔王の攻撃を正面から受けようというのか、ポピーは宙に留まったまま回避の行動を取らない。
それは単に、ミルドラースの視線をひきつけるためのものだった。ポピーの竜の背に乗るビアンカもティミーも、彼女を信じ切って落ち着いてその場に待つ。
ミルドラースの死角から突っ込んできたアンクルが、デーモンスピアの先をその首へと突き立てる。本心では、敵の視界を奪うために目を狙いたかった。しかし大魔王の視界に入ることを避けるために、背後から首を狙ったのだ。膨張し切ったような大魔王の身体は、首も肉に埋もれ、容易に損傷を与えることができない。竜の皮膚のように、決して硬い皮膚ではなかった。デーモンスピアの槍先は難なくミルドラースの赤黒い皮膚に沈んだ。しかし余りにも分厚い肉に守られている身体は、アンクルの攻撃を大したものではないと示しているようだった。
ミルドラースの翼が大きくはためく直前、アンクルは素早くその場を離れた。しかし続けて振るわれた棘のついた尾に薙ぎ払われ、力の盾で受け止めつつも、アンクルの身体は宙に吹っ飛んだ。
そのまま底のない魔界の谷底深くへと落ちかねなかったアンクルを、黒竜リュカが竜の手で掴んで救う。リュカの背に乗るピエールがすかさず回復呪文ベホマを施し、束の間気を失っていたアンクルはすぐに目を覚ました。アンクルは、見上げる黒竜の目を見て、そこには紛れもない人間のリュカがいるのだという強い意志を感じて安堵し、自らリュカの手を離れた。
リュカは黒竜の姿となっても、明確に己の意志をその光ある漆黒の目に表していた。リュカを振り向くミルドラースと正面から目が合う。ミルドラースの両目は不気味な弧を描き、閉じない口から無駄なほどの牙と、大きな舌をだらりと垂れている様に、黒竜の漆黒の瞳はただただ冷たく光る。もはやこの者は、己の姿がどのような有様になってしまっているのかを理解することもできないのだろう。ここまでの化け物と成り果ててしまえば、今から戻ることも、帰ることも叶わない。
黒竜の姿で、リュカは思わず呻き声を上げた。母マーサはきっと、この者も戻れると信じて、対話を続けていたに違いないのだ。ジャハンナの町に住む者たちのように、未来にはあの魔界の町で共に暮らすこともできるのではないかと、そんなことも考えていたのかも知れない。そのような母への裏切りも、ミルドラースの醜悪極まる姿に含まれているのだと思い、黒竜リュカは一直線にミルドラースへと飛びかかって行った。
何者も敵ではないと言わんばかりに、ミルドラースは黒竜リュカを正面から待ち受ける。悪魔神官の手にしていた棍棒を彷彿とさせる、棘の尾を振り上げる。笑みすら浮かべて待ち構えるミルドラースの正面から、黒竜リュカは決してそのまま突っ込んでいくような野暮はしない。両翼を一瞬で広げ、宙で急停止したかと思えば、ミルドラースの頭上へと回転しながら身を翻す。ミルドラースと戦っているのは、リュカ一人ではない。黒竜リュカの背には、頼りにしている戦友がいる。
黒竜の反転した動きを追い、ミルドラースの視線が上を向く。そこには既に、二体の戦士の姿が間近に迫っていた。プックルとピエール。アンクルが狙い切れなかった両目に狙いを定め、同時に爪を、剣を向けた。しかし的を外した。ミルドラースが直前に、分厚い瞼を閉じ、目を守ってしまった。プックルの炎の爪は大魔王の分厚い瞼を焼きつけ、ピエールのドラゴンキラーもまた深く瞼を切り裂いたが、ミルドラースの視界を奪うには至らない。これほど分厚い肉に包まれ、守られている身体だというのに、まだ痛みを感じるのか、ミルドラースは大口を開け、涎を飛ばしながら叫び声を上げる。大袈裟に顔を横に振る動きのために、プックルとピエールはミルドラースの顔の上から払われてしまった。プックルを黒竜リュカが、ピエールをアンクルが拾い上げ、すぐさま追撃をと大魔王を見据える。黄金竜ポピーもまた、大魔王の隙を窺い、動き出す時を見据えている。
ミルドラースは、実は大した損傷でもない瞼の傷に耐えられないと言うように、開けた大口の中から炎を吐き出した。それは忽ち灼熱の炎となり、まるで子供が自棄を起こしたような勢いで辺り構わず吐き散らされる。黒竜リュカがそれに対抗するように激しい炎を吐けば、同じ方向から構えた黄金竜ポピーもまた父に習い、激しい炎で応戦する。いくら大魔王と言えども、呼吸と関係なくいくらでも灼熱の炎を吐き続けられるわけではない。
持ち堪え、灼熱の炎が止む。皆を守ろうと、身体を張っていた黒竜も黄金竜も、身体の前面に大火傷を負っている。それは誰もが分かっていた。しかし今はとにかく、あの醜悪を見せる大魔王を倒さなくてはならないと、各々の役目を各々考えている。
この状況、味方の傷を回復できるのはティミー、ピエール、そして賢者の石を手にするビアンカ。アンクルは己の損傷ならば、装備する力の盾に治癒を頼ることができた。
ティミーが天空の剣を掲げているのを見て、ピエールは主であるリュカを置いて、近くに飛んでいる黄金竜ポピーの傷を癒すべく、ベホマの呪文を唱えた。ここでリュカの傷を癒すことを、リュカ自身が望んでいないことなど分かり切ったことだ。天空の剣に神の光が宿るのに合わせるように、その隣でビアンカが既に呪文の発動の体勢を見せていたのだ。
ミルドラースの巨大な赤黒い身体を、ティミーの放った凍てつく波動が包み込む。呪文反射マホカンタの膜が、ミルドラースの身体から剥ぎ取られて行く。その途中で既に、ビアンカは再び作り上げたメラゾーマの大火球を大魔王の顔面目掛けて放っていた。
鈍重な外見を持つミルドラースの動きは、見た目に違わず、決して素早いものではない。無駄と言う他ないほどに膨れ上がった身体を動かすのは、ミルドラース自身も想定していない鈍さを伴うのだろう。ビアンカの放ったメラゾーマは狙い通り、ミルドラースの顔面に命中した。しかし巨大火球のメラゾーマでも、ミルドラースの顔面の一部を焦がすに過ぎなかった。あまりにも大魔王は巨大な敵だった。
追撃をと向かうのは、リュカ自身だ。ビアンカのメラゾーマがミルドラースの顔面を捉える前に既に、黒竜リュカは大魔王に向かい飛んでいた。その背に控えるプックルが、リュカが手にする武器の如く、鋭い青の目で飛びかかる位置を見定める。ピエールは灼熱の炎を食らった損傷を癒すべく、黒竜リュカに回復呪文を唱えようとした。
しかし目の前の大魔王の身体から、怒りや憤りの感情の発露がそのまま力となったかのような気配が飛び出した。飛びかかろうとする黒竜リュカの動きが宙に止まる。以前までの、理性を失ったような黒竜であれば、そのまま大魔王へと突っ込んでいただろう。しかし今は、背中にある大事な仲間の存在を、共に戦っている家族も仲間も大事なのだと、リュカは黒竜の姿となりながらも決して我を忘れていない。
リュカは黒竜の姿のまま、その場に身構えた。併せてプックルもピエールも、リュカの背中に防御態勢を取る。ミルドラースの巨大な赤黒い身体から発せられた大爆発に、黒竜リュカも、黄金竜ポピーも、アンクルもまた、吹き飛ばされてしまった。その大爆発は、まるで駄々をこねるだけの子供の様な、ただただ感情的なものだった。自らを大魔王などと名乗れど、その芯となるような思いも考えも、この者にはない。ただ目の前のものが鬱陶しい、己に是と言わない者が許せない、己を認める者だけが是なのだと、その思いとも呼べない思いはひたすらに浅い。
そのような者が、力だけを持ってしまったという悲劇だ。その点においては、リュカの仇敵ゲマも似たような者だった。しかしゲマでさえ、力を求めるような窮した過去があったことを、リュカは母マーサの見せた水の景色の中にそれを知った。そしてその瞬間に、リュカが長年抱き続けてきた憎しみの感情が図らずも、壊れてしまったのだ。
一体このミルドラースと言う者が、これほどまでに醜悪なものへと変貌を遂げてしまったのは何故なのか。今のこのような状況となってはそれも知る由もないことだが、この者も元は人間。たとえばゲマのような過去があったとすれば、この者にも少しは救いがあるのではと思いながらも、リュカは己の背中から飛ばされてしまったプックルを追い、滑空していく。
宙で辛うじて留まりながら、己に力の盾で傷を癒すアンクル。同じく吹き飛ばされた黄金竜ポピーは、背にある母と兄を守り切ることができず、ただ己の身を守るのに必死だった。その背で、ビアンカは黄金竜の背にしがみついていられず、宙へと落ちかけた。その手を、ティミーが必死に掴む。しかしティミーもまた自身を支えていられず、歯を食いしばり、心の中で謝りながら、黄金竜の背に天空の剣を突き立てた。ポピーはただ耐えた。ティミーは黄金竜の背に突き立てた天空の剣を軸に、母の手を左手に強く掴み、宙に放り出されることからどうにか逃れた。
間髪入れずに、ミルドラースの巨体から強烈な魔力が迸った。黒竜リュカは、今の己の身を纏う竜の硬い鱗がぼろぼろと剥がされたような感じを覚えた。それが、敵の防御力を剥ぎ取る呪文ルカナンであろうことには気づいたが、ミルドラースの放ったものは、それだけに留まらなかった。
大魔王の身体が浮かぶ周りに、地上世界の景色を見せる岩石が相変わらず浮かんでいる。ミルドラースの放ったルカナンの呪文は、今目の前で敵対しているリュカたちに向けて放たれたものではなかった。岩石に見える地上世界の景色が、一層黒い暗雲に覆われ、まるっきり見えなくなってしまった。同時に、ミルドラースの浮かぶ更に上、渦巻く暗雲の中心、暗雲などよりも更に深い黒の空間が、僅かに開きかけているのを、リュカは見た。
地上世界と魔界とを繋ぐ門を守っていたのは、エルヘブンの民。そして魔界の門を開く力を唯一持っていたのは、リュカの母マーサだった。そのマーサはこの世を去り、魔界の門は、その主たる門番を失い、今や封印の力を失うばかりの状況。そして、大魔王ミルドラースは、大魔王としての欲望に忠実に、地上世界へと手を伸ばしかけている。
黒竜リュカの巨大な竜の体の中に、母マーサから譲り受けた命のリングの力が宿る。あの巨大で強大なる大魔王が地上世界へ放たれれば、地上にある命と言う命が作為的にも無作為的にも蹂躙されてしまう。それを防ぐべく、リュカは黒竜の姿のまま、命のリングに宿る力に願う。地上の世界を危険に陥れることを誰も望んでいない。それは人間も魔物も同じはずだと、黒竜リュカは渦巻く暗雲の中心に見える黒を潰そうとする。
それに加勢するように、ポピーの背の上で体勢を立て直したティミーが、天空の剣を暗雲に向けて構えた。大爆発を受けて、母と兄を庇い酷い怪我を負う黄金竜ポピーには、その背でビアンカが賢者の石を手に祈りを捧げる。そして天空の剣から放たれた凍てつく波動が、中心の黒を囲む暗雲の渦に行き渡り、まとまりかけていた暗雲は力を失い、散った。
ミルドラースの黒く塗りつぶされたような目が、歪んだまま勇者ティミーを見据える。大魔王の行動は、ただの衝動であるために、躊躇がない。膨張した腹には常に力が溜まっているのか、何の予兆もなく大口から吐き出された灼熱の炎の嵐に、リュカたちは皆巻き込まれた。応戦するための猶予も与えられず、リュカたちはたまらずその場に悶え苦しむ。
リュカたちが揃って苦しむ様子を目にし、ミルドラースは灼熱の炎を吐くのを止める。たとえば、そのまま凄まじい炎を吐き続け、リュカたちを葬ることも可能だった。しかし、人間の欲望と言うものにはキリがないことを示すかのように、ミルドラースの、涎も垂らすがままの閉まらない口には、その醜悪な外見そのものの醜悪な笑みが浮かんでいた。敵となる者の苦しむ姿が、ミルドラースにとっては心地よいものだった。しかも、その敵と言うのは、世界を救うために生まれてきたとされる勇者や、地上世界のどこかも知らない国の王だと言う。
無限とも思えるような力を手にしたミルドラースにとって、灼熱の炎を吐き出すことなど些細な事に過ぎない。いつでもこの力は見せつけることができる。敵を片づけるよりも深い欲望は、敵となる者の苦しむ姿を存分に楽しむことだった。しぶとく立ち上がったところで再び苦しめてやる。そうして己の力を誇示しようとするミルドラースの見せる醜悪な笑みには、歪み切って、戻れなくなってしまった、人間の業の深さがありありと現れている。
壇上から見下ろす景色。優位の表れ。多くの人々が己を見上げ、己を崇めている。一国の主というわけではない。が、由緒ある血筋の者なのだと、そう言われて育った。
一国の王も頼りにする参謀、という立場。己を頼りにする王も民も、全てが愚かと感じていた。誰も己を否定する者がない。全て、受け入れるのみ。何故否定しないのか。それは偏に、愚かだからに違いない。否定するような頭もないのだ。
己が是と言えば是、否と言えば否。この状況は、ただ楽しい。一国を滅ぼすのもワケはない、と思うほど。国を滅ぼすなどという考えが頭を過るのは、あまりにも人間と言うものが愚かに見えるからだ。
壇上から見る人間たちは、地を這う蟻にも等しい。その一つ一つに、尊い命と言うものがあるとは感じられない。己から見る人間たちは、ただの単体であり、集合体であり、それだけのものだ。命があるようには見えない。ただ意味もなく動いているだけ。しかしその集合体や単体をまとめるのには、己の力が必要だという。それならばと、この場所に居続けているが、己のような者が本来いるべき場所がここではないことなど、分かり切ったことだ。もはや、人間の存在が、ただの丸や棒のようなものにしか見えない。
このままでは、己の人生を生かし切れない。そのような損失があってなるものか。もっともっと、己の存在が輝くべき場所があるはずだと、そう考える彼の視線は、やはり己にのみ向いていた。
それ故に彼は、己のいるべき場所を目指して、志高く、旅に出た。自分を探すための旅。己は必ず、何者かになれるはずだと信じて、旅に出た。目の前にしていた馬鹿げた人間たちの集合体ではなく、もっと己を生かせる場所があるはずだと信じて、もっと己が生きるに値する場所があるはずだと信じて、希望ある旅に出た。
旅の目的。それ自体が漠然としていた。己を探す旅とは。己を見つけようとして、己を見つけ切れる者などいないに等しい。己を見るには、他者を見ることが必要なのだと言うことを、他者から見る己の姿に目を向けることが必要なのだと、彼は終ぞ知るに至らず……。
Comment
ああ、いよいよですね……もうモンスターのみんなにもすっかり感情移入してしまいました
スミス 様
すみませんっ! こちらにコメントをいただいていましたね。お返事をせずに過ごしてしまい、まことに申し訳ございませんでした。今更ですがこちらにお返事させていただきます。
仲間になったモンスターたちには私も感情移入していて、いったい誰にどれだけ場面を設けられるかと考えるのに苦心していました。なるべく平等にと思いつつ、どうにも差が出てしまうなぁと。……と、そのような感じのまま、どうにかラスボスを倒せました。エンディングを続けて書かなければならないのに、なんだか脱力してしまい、なかなか書けないという……。モチベーションを取り戻さなくては(汗)