世界の仕組み
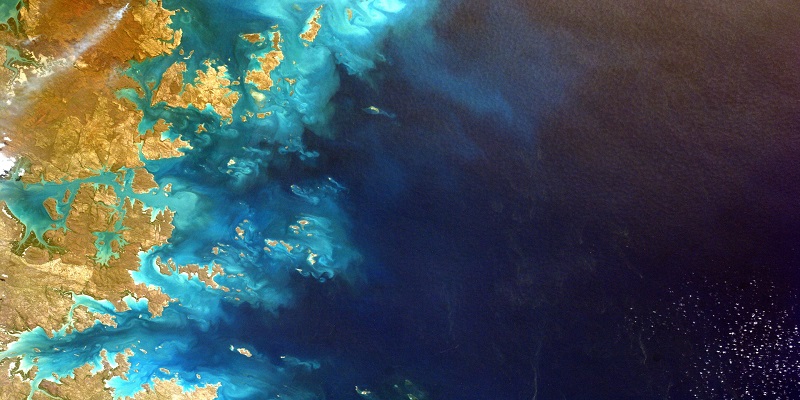
リュカの旅の終着点は妻の救出であり、父の遺言に従い母を救い出すことだ。途中、目的を見失いそうになることも多かれ少なかれあったが、彼の目指すところは一貫している。そして旅の途中でその存在を知った天空城、その城に住まうと言われるこの世の神というものがいると知れば、彼はそれが旅の終着点に連れて行ってくれるものだと心のどこかで信じていた。リュカ自身はまるで神様と言う存在を信じていない性質だが、もしそのようなものが本当にこの世にいるのならば、必ず妻と母を救い出してくれるのだと、世界のそこここで神様を信じている人間と何ら変わらない期待を抱いていた。
今、リュカの目の前には竜神が堂々たる風貌で巨大な玉座に座っている。人間が何人も乗れそうな玉座さえ窮屈そうに身を縮めて座しているマスタードラゴンは、リュカたち人間が期待するような全知全能の神というわけではなかった。竜神は言わば、生と死の神だ。生み出すことと、失くすこと、しかもその対象は人間たちが住む地上界であり、たとえばこの世界が魔界の力に屈した時には、竜神はその力を振るうと言う。その時、リュカたちが生きる世界は全て無くなる。そして神は再び、世界を創り直す。
あくまでもこの地上界の神であるマスタードラゴンの力は、魔物らの蔓延る魔界に及ぶことはない。それは神の慈悲とも呼べる措置であり、魔物たちの住む世界への干渉をマスタードラゴンは善しとしなかった。魔界には凶悪な魔物たちが住んでいると言うが、地上界や天空界への脅威とならず、魔界の中で生きる分にはその存在を否定はしない。完全に分けた世界の中でそれぞれ生きている分には、本来問題の起こりようもない。まだ世界の始まりの時代、生まれたての赤ん坊のようなものだった神は、純粋な心と共に、そのような決まり事を作って世界に守らせた。
万が一、この世界の均衡が崩れ、魔界が人間界に、はたまた人間界が魔界に侵入し脅かすようなことがあれば、世界をまた創り直せばよい。神はどちらの世界へも慈悲を示す一方で、生き物一つ一つに対しては嘘のように無慈悲だった。
世界の決定である神の意志を、途中で翻すことは許されない。初めに生まれた決まり事に、神自身も背くことはできない。もし世界の決定を簡単に破るようなことが起これば、それは即ち世界の混乱に繋がる。誰も決まり事を守らなくなり、秩序が失われる。誰もが自分勝手になり、他の事に、他の人に構わなくなってしまう。そのようなことを避けるためにも、竜神自身、自ら創り出した決定を破ることはできないのだ。
魔界の力が日に日に強まっているという。その力は明らかに人間界へと手を伸ばしており、マスタードラゴンは魔界の王が人間界を手に入れようとしているのだと、どこか他人事のように言う。神がここでできることは、魔界の力に抗うために、人間に助力するということだ。神自らが力を発動してしまえば、世界は忽ち消えてしまう。強まる魔界の力に抗えるのは人間であり、世界を救うために生まれた勇者にその力が備わっているはずだと、竜神はまだ小さな子供であるティミーをその鋭い琥珀色の目で見つめる。
玉座の前に居並ぶリュカたちに、玉座の竜神は一つ一つゆっくりと説いていた。話を何度聞いたところで、リュカたちが為すべきことはただ一つだ。人間であるリュカたちが力を合わせて、この世界を守り切らなければならないと言うこと。人間が負け、魔界からの侵入を許し、魔界の王が人間界に手を伸ばしてきたその時、竜神は破滅の力を発動してしまう。その力は恐らく、魔界の王をも凌駕するものなのだろうが、人間界を完全に破壊してしまうほどの力の前に生き残れる人間はいない。たとえ魔界の王に勝利したとしても、その時既に、人間たちはこの世から敗れ去っているのだ。
いくら話を聞いても、リュカは目の前の神がこの世界を手の平に乗せて遊んでいるという感覚が拭えなかった。マスタードラゴンを見るリュカの目つきにいつもの優しさはない。その視線は子供たちから見ても仲間たちから見ても、明らかに冷徹さを滲ませている。リュカの中にやり場のない怒りと諦めがあるのだった。
「僕がもっと強い父親だったら良かったんだけどね」
勇者である息子を持つ父親は恐らく、世界を救わんとする息子を誇りに思い、勇者の使命を負った息子を信頼し、世界を救うためにその背を押さなければならないのかも知れない。しかしリュカにはどうしてもそれができない。子供はまだ十歳にも満たない子供で、世界を救うなどと言う大それたに巻き込むなど言語道断と思ってしまう。
しかし物語によくあるようなそんな理想の父親像など、理想だから物語になっているのだろう。人々が作る話と言うのは、人々が夢見る空想が詰まっている。現実にその立場に立たされれば、まるで反対の思いを抱くこともまた真実であったりする。
「お父さん、ボクはさ、ボクが勇者で良かったって思ってるよ」
ティミーの言葉はいつでもリュカの心を勇気づける。ティミーは決してリュカを元気づけようと声をかけているわけではない。彼はただ、自身が感じていることをそのままリュカに伝えているだけなのだ。
「だってお父さんも、おじいさまだって、本当は『自分が勇者だったら』って思ったんだよね、この剣を見た時に」
そう言いながらティミーが手にする天空の剣は、天空城の玉座の間に入り込む陽光を受けて眩しいほどに煌めく。手入れなどせずとも自浄作用でもあるのだろうか、天空の剣は常に美しい刀身を見せる。リュカも、恐らく父パパスもまた、天空の剣を使えない自分の存在を呪いたいと感じた。魔界の扉を開く力を自分が持てたなら、迷わずその力を頼りに魔界の扉を開いて見せるというのに、自分にその力は与えられず、まだ子供のティミーにその力が授けられてしまった。
「ボクがお父さんとおじいさまの夢を叶えられるんだって思ったら、ボクが勇者で良かった~って思えるんだ。本当だよ」
彼は自分の口から出る言葉がどれほど強く勇気溢れるものなのかということに気付いていない。ティミーは本心からそう思い、本心から父と祖父の役に立てることを嬉しく思っている。
「私も、今じゃお兄ちゃん以外に勇者なんていないって、そう思えるの」
ポピーは双子の兄が勇者であることに一種の悔しさを抱いている。双子なのだから、負う使命を二つに分けて欲しかったと、今でも彼女は正直思っている。しかし勇者としての力を持つ兄と持たない自分とを比べれば、この違いは歴然で抗いようもないのだと意識して認めているのも事実だ。兄は天空の武器や防具を手にして戦うことができるが、彼女にはその内の一つでも手に持つことはできない。勇者選定の伝説の武器防具は非常に非情な代物だ。
「こんなに恵まれている勇者もいないでしょ? だってお父さんは王様でとっても強くって優しくて、双子の私は大魔法使いだし、それに魔物の仲間だって沢山いるのよ。勇者が一人で世界を救うんじゃないんだもの。お兄ちゃんと一緒に、みーんないるんだから」
勇者は生まれるべくして生まれたのだろうと、ポピーの言葉にそう思える。リュカには多くの仲間がいる。グランバニアの屈強な兵士らは皆、リュカの仲間と呼んでもよい者たちだ。国を越えてラインハットもテルパドールも、国同士の結束を深めているところだ。それもこれも、リュカがグランバニアの国王であることで、世界中にその力を伸ばすことができているのだ。人間界が脅かされている今、国も大陸も超えた結束が必要となる。リュカがグランバニアという一国の主であることもまた、ティミーが勇者であることと同様の使命があると考えても、不思議なことではない。
勇者ティミーには彼にのみ装備することを許される天空の剣や兜、盾がある。息子の神々しい輝きを放つ装備品を目にしながら、リュカは今、自身が手にしているドラゴンの杖に目を落とす。神の力が封印されていたボブルの塔で手に入れた、こちらもまた神の力宿る竜の形を模した大振りの杖だ。竜がそのまま杖となったような形状で、杖頭には緑の竜の頭が、そのすぐ下には胸に抱くようにして桃色の宝玉が収まっている。下方に向かい竜の腕が伸び、杖先は爪の鋭い竜の足が桃色の宝玉を鷲掴みにしている。明らかに魔力の込められた二つの宝玉だが、杖を手にしているリュカにはその力がどのようなものなのかを感じ取ることができない。
「その杖はドラゴンの杖。私の力の一部が込められている」
リュカの思考を読み取るかのように、マスタードラゴンが玉座にいながらリュカに話しかける。相変わらず竜神の口が動くことはなく、低く厳かなその声はリュカたちの頭の中に直接響いてくる。
「世界を救う使命を負う勇者の、助けとなる杖だ。勇者の最も傍で、勇者を常に守り続ける者がその杖を手にすることができる」
マスタードラゴンの言葉を耳にし、その杖をリュカが手にしている状況は、誰もが自然と理解してしまう状況だった。杖の存在意義を知らされれば、リュカは他の誰にもこの杖を渡すことはできないのだと自覚する。父パパスがグランバニアの紋章の彫られた剣一つでリュカを守ったように、リュカは神の力宿るこの杖でティミーを守り切るのだという思いが自ずと強まるのを感じた。
マスタードラゴンは勇者ティミーを見つめながら、その中にかつての勇者の姿を重ねていた。
かつての勇者は孤独だった。その宿命を負わせたのはマスタードラゴンだ。人間と天空人の間に生まれた勇者は、世界で初めてで、唯一の存在だった。本来ならば生まれるはずのない人間と天空人の双方の血を持つその者に、マスタードラゴンはまるで呪いの一つでもかけるように世界の命運を負わせた。無事にその役目を遂げた時に、勇者を勇者の宿命から解き放ち、天空人の一人としてこの城に迎え入れようと、いかにも神らしくその者の運命を決めつけていた。
数多の試練を乗り越え、導かれし者たちと共に世界を救った勇者は、天空城に戻ることを拒んだ。マスタードラゴンには勇者の心が分からなかった。地上には善悪入り乱れた人間たちが住む世界が広がっている。空高く浮かぶ天空城には、暗黒世界の脅威が去った今となって平和な時間だけが流れて行く。二つの世界を比べれば、どちらが良いかなど考えるまでもないと思っていた。
平和な世界を取り戻した後、勇者が地上で暮らす姿をマスタードラゴンは時折覗いていた。勇者はかつての仲間たちと会う時、いかにも人間らしい朗らかな顔をしていた。嫌なことを言われれば素直に嫌な顔をした。理不尽な言葉を投げつけられ、怒りだすこともあった。静かな夜に一人、涙を流していることもあった。その姿全てが、人間そのものだった。
人間も悪くないのかも知れないと、マスタードラゴンはかつての勇者のその姿にそう思い始めていた。自分は竜神として地上を見ていたつもりだったが、それはただ見下ろしていただけだったのかもしれない。人間と言う生き物を深く知るためには、自ら地上に降り、間近に人間と接しなければならないと、マスタードラゴンは時折人間に姿を変え、地上に降りることが多くなった。
かつての勇者と導かれし者たちが取り戻した平和がいつまで続くかは竜神にも分からない。しかしその平和が破られようとする時には再び、勇者が現れるという運命はマスタードラゴンが定めたものだ。その時にはマスタードラゴン自ら、勇者の力になりたいとそう願えるほどまでに、神は人間の持つ独特の魅力を理解するようになっていた。
もしその時が訪れた時には、マスタードラゴン自身も人間の力添えができるようにと、竜神はドラゴンの杖という武器を新たに生み出した。神自身が直接、人間たちが住む地上界で力を振るうことはできない。その代わりに神の力を宿すこの杖を手に取る者に、勇者を援ける力を与えようとしたのだった。
マスタードラゴンの数百年前に上る過去の記憶がリュカたちに伝達することはない。リュカはただ、勇者を援けるための力を得たのだと、ドラゴンの杖に光る桃色の宝玉を見つめた。
「その杖は私の一部のようなものだ。宝玉に強く念じれば、私の力の一部が発動するだろう」
「えっ!? それってこの世界を壊しちゃうってこと?」
ティミーが慌てたようにそう言うのを、マスタードラゴンは穏やかに見つめている。
「そうならないための杖なのだ。これからもまだそなたたちの戦いが続く。その際に使ってみれば、何が起こるか分かるだろう」
「何が起こるか、教えていただけないんですか……?」
「楽しみは取っておいた方が良いというのも、私は人間から学んだことなのだよ」
威厳を感じるような脳内に響く声で、悪戯めいた言葉を伝えるマスタードラゴンはやはり人間のプサンの名残が感じられた。大きな灰色の竜の翼を動かしても、そこに神の畏れを感じるのではなく、ただ人間のプサンが背中のかゆいところに手が届かないで身じろいだのだろうかと思ってしまうのだから、自ずとポピーの身体を包んでいた緊張も薄れて行く。
仮にも神様なのだからもう少し威厳を保った方が良いのではとリュカが思っても、長い時間を人間の姿で過ごしていたマスタードラゴンは気を抜けば人間らしさを見せてしまうようだ。今も何やら眠そうに目を半分閉じたような状態で、一応神の威厳を保とうと思っているのか、欠伸を噛み殺しているのがリュカには分かった。天空人の兵士らは堪える欠伸の隙間に見える竜神の鋭い歯に恐れ戦いていたが、リュカは呆れたように剥き出しの歯を見つめるだけだ。その姿はプックルが欠伸をしかけている姿と変わらないようにリュカには見えている。
「僕たちは長い間、と言ってもあなたにとっては短い時間かも知れませんが、妻と母を捜して旅をしています。神様のあなたなら、二人がどこにいるか分かりますか」
リュカの口調は、神様なら知っていて当然とでも言うようなものだった。マスタードラゴンは我慢し切れた欠伸の息を鼻から噴き出すと、涙目になった琥珀色の目を瞬かせてリュカを見下ろす。
「そなたの母の名は」
「マーサ」
「妻の名は」
「ビアンカ」
「ふむ」
そう言ったきり、マスタードラゴンはまるで瞑想を始めるように静かに目を閉じた。誰もが時を止めたように動かない。マスタードラゴンの深い思念が世界を駆け巡る。今の世の中、数百年前に比べて人間の数はずっと少ない。かつての世界よりも、人間たちはその世界を狭めていた。国の数も少なく、町や村も僅かに点在するだけだ。それは人間同士の争いに依るものだったことを、リュカたちはほとんど知らない。
世界を駆け巡るのだから時間もかかるだろうと、リュカはひたすら目の前の竜神の答えを待っていた。しかし竜神の大きな鼻から規則正しい呼吸が穏やかに繰り返されるのを耳にすると、リュカは思わず手にしているドラゴンの杖の宝玉に念を送る。
「はっ!? いかんいかん、少し眠ってしまったようだ」
「……この杖の宝玉に念を送れば、ちゃんとあなたに通じるって分かって良かったです」
「マスタードラゴン様も復活されたばかりできっとお疲れなのでしょう」
「人間の姿からこうしてお戻りになられたのですから、元の身体に慣れるのにも少々時間がかかるものと……」
天空城を浮上させ、竜神の封印された力を取り戻したリュカに対し、天空人らが強く出ることはない。それ故に彼らの主であるマスタードラゴンに対して明らかに不遜な態度を取るリュカに彼らは穏やかに宥める言葉をかけるだけだった。
「確かなことは言えんが、二人ともこの地上には見当たらないようだ」
「二人とも?」
期待していた答えが返ってこないことに、リュカは怒りや悲しみよりも、驚きに少し目を見開いた。母マーサがこの地上の世界にいないことは既にリュカたちも知っている。父の遺言によれば母は魔界に連れ去られているために、この世界にいないという竜神の言葉は確かに合っている。しかしビアンカまでもがこの世界にいないと言う。彼女もまた母と同様に、魔界に連れ去られてしまったのだろうかとリュカは思わず顔を歪める。
「お父さん、お母さんは、その……今は石にされているのよね?」
ポピーの言葉にリュカは小さく何度か頷く。当然、マスタードラゴンにもポピーの言葉が聞こえており、竜の大きな目が小さな女の子に向けられる。
「石の呪いをかけられた人間は、私にしてみればそこらの石と変わらない」
マスタードラゴンはただ己の真実を述べているに過ぎないのだが、配慮も何もないその言葉にリュカは思わず竜神を下から睨みつける。ドラゴンの杖を前に構えるリュカを、天空人の兵士らが抑える。
「さすがの私も、世界中の石一つ一つに思念を送ることはできない」
「でも、それって逆に考えれば、やっぱりお母さんはこの世界のどこかにいるかも知れないってことだよね。まだまだ望みがあるってことだよ、お父さん!」
存在を否定さえされなければ良いのだと、ティミーはあくまでも前向きに勇者としての使命を果たす。ティミーの声音はいつでも沈みかける仲間たちの心を浮上させる。リュカも今までに何度となく、息子の根っからの明るさに救われてきた。
「おばあさまもこの世界にはいないだけで、きっと今も生きてお父さんを待っているはずよ。だから、また一緒にさがそうね、お父さん」
結局は神が封印していた能力を解放しても、妻も母もその所在は分からない。マスタードラゴンの力も生命の感じられない石には通じず、魔界という異世界に伸びるものでもないらしい。石の呪いに秘められた本当の意味を今になって知らされたような気がした。
「ふう。この姿でいることにこれほど疲れを感じるとは。長いこと人間の姿でいたために、私も体力が落ちたのかも知れない」
到底神様の発言とは思えない疲労を思わせる言葉を吐き、マスタードラゴンは今度は遠慮なく大口を開けて欠伸をした。天空人たちは目を丸くして主たる竜神のその間の抜けた姿を見ている。欠伸の息が玉座の間に広く行き渡る。部屋の端に寄る魔物の仲間たちが竜神の息を浴びて、思いの外熱のこもる息に顔をしかめている。ふとした瞬間に竜神が灼熱の炎でも吐いてしまうのではないかと、僅かな緊張が走っていた。
「少しこの姿に慣れるのに時間が必要だ。しばし眠るとしよう」
そう言うなり翼を折りたたみ、身体を丸めて首を足の上に寝かせる。リュカが話しかけた時には、マスタードラゴンは既に夢の世界へ旅立っていた。神様ともなれば、眠ると決めた瞬間に眠りに就くことができるようだ。思い悩んで眠れないということもないのかも知れない。
リュカは同じように唖然としている天空人に話しかける。マスタードラゴンは安らかな寝息を立てて、リュカの声にはまるで気づかない。
「しばし眠るって、どれくらい寝るんでしょうか」
そう問いかけながら、リュカは嫌な予感がしていた。この世界を生み出したマスタードラゴンが休む『しばし』という時間を、人間の世界に当てはめることなどできない。彼の言うしばしという時間は、天空人たちが過ごす時間に当てはめる方が適当だ。嫌な予感しかなかった。
「私にも分かり兼ねますが、恐らく数か月は……」
「……やっぱり。一日、二日の話じゃないとは思ったんだ」
何せこの城にいる天空人らは、湖の底に沈み続ける天空城の中でひたすら眠り続けていたという強烈な生命力を持っている。その期間は二十年を悠に越えているのだから、この世の神様の昼寝ともなると数か月単位で時を過ごすのも頷きたくないが理解はできた。
「あっ! それじゃあ神様を起こしたかったら、さっきのベルを鳴らしてみればいいんじゃないかな? そうしたらベルの音できっと起きてくれるよ!」
「目覚ましのベルじゃないんだから……そういう使い方はあまり良くないと思うんだけど」
「でもいつでも呼んでいいって言ってたから、もし神様の力が必要になった時には、ベルを鳴らして助けに来てもらおう。それくらい、してもいいですよね?」
リュカがそう問いかけると、天空人の兵士は二人で顔を見合わせ、玉座で安らかな寝息を立てて眠る竜神を見上げて、少し考えるような顔つきをしながら答えた。
「マスタードラゴン様がリュカ殿にお渡ししたものですから、構わないと思います。その時には必ず、あなた方のところへ向かうでしょう」
「あー! そう言えばボクたちまだマスタードラゴンが空を飛ぶところを見てないよ! 先に飛んでもらえば良かったなぁ。見たかったなぁ」
「じゃあ、今起こしてみる?」
「……お父さん、マスタードラゴンのこと、神様って思ってないでしょ」
「そんなことないよ。ちゃんと思ってるって」
ポピーに咎められるようにそう言われたリュカは、いかにも表面を取り繕うように応じながら、一先ずこの場で天空のベルを鳴らすことは控えることにした。復活したばかりの竜神が、人間の身体から竜神の身体に馴染むまで時間がかかるというのもとりあえずは頷ける。いざという時に確かに竜神に協力してもらうためにも、リュカはこの場では大人しく天空のベルを道具袋の中に収めておいた。
「リュカ王、一度グランバニアに戻り、オジロン殿やサンチョ殿へ現状の報告をした方が良いかと思われますが」
マスタードラゴンが玉座ですやすやと眠る中、リュカたちは玉座の間の端に寄ったところで円陣を組むように頭を突き合わせていた。魔物の仲間たちは魔物の性質故か、神様であるマスタードラゴンの傍に近づきたくはないようだ。リュカとしては見た目にも魔物の仲間たちと変わらないマスタードラゴンの竜の姿に、まるで仲間たちと同じような感覚で接してしまうのが本当のところだ。
その中でサーラが落ち着いた様子でリュカに話しかけたところだった。
「そうですね。我々の目的はお二人の救出ですが、竜の神にもその所在が分からないとなれば、一度国に戻り落ち着くのが良いと思います」
ピエールにもいくらかの神への失望が見え、リュカは勝手な仲間意識でピエールの意見に耳を傾ける。プックルもリュカの隣で床に寝そべるようにして、半分閉じたような目で玉座に眠る竜の神を横目に見ている。彼もまた、期待していた神ではなかったことに、内心拍子抜けしているのだろう。
「お父さん、それがいいよ。一度グランバニアに戻ろうよ。久しぶりに城で食事もしたいしさ!」
「ルーラで戻ればすぐなんだけど、またこの天空城に戻ってこられるかな」
リュカたちはボブルの塔からこの天空城へ戻るのに、ルーラを使用していない。それと言うのもリュカにもポピーにも、一つ所に留まることのない天空城の位置を正確に脳裏に描くことができず、ルーラでの移動が叶わなかったのだ。今でこそ、テルパドール西の大陸に留まっている天空城だが、本来この雲を纏う巨大な城は青空の只中に浮かんでいてこその城だ。そのためにリュカにもポピーにも、空に浮かぶ天空城や、天空城から眺める空の青や雲の白や陽光や、はたまた地図を広げたように見える世界の景色がその脳裏に浮かんでしまう。
「あの、リュカ殿、非常に申し上げにくいのですが……そろそろこの天空城を動かそうと思っています」
リュカたちが話しているところへ、天空人の兵士が一人近づき話しかけてきた。天空城の操縦室はこの玉座の間の真下にあるが、操縦できるのはリュカたちだけではなく、当然のように天空人の中にも操縦可能な者は数人いる。
この天空城は雲に乗り、風に乗り、世界を巡りつつ世界の様子を見て回る義務を負っている。天空城の浮上に大いなる貢献を果たしたリュカたちには特別にその操縦する権利を与えられているが、彼らがこの城を離れている間に延々と天空に浮かぶはずの城を地上に留めておくのは好ましくないのだと、天空人の兵士は説明する。ただでさえ、リュカたちがボブルの塔へ向かっている間、天空城は一度も天空に浮かぶことなく地上に留まり続けていたのだ。
「あまりにも地上に留まっていると、再び城が浮かばなくなるのではないかと言う不安もありまして……」
リュカたちが天空城の浮上に成功するまで、長い間深い湖の底で眠り続けていた天空城だ。同じように湖の底でひたすら眠り、浮上の時を待ち続けていた天空人にとって、地上の景色が物珍しく留まりたいと思う反面、長く地上に留まることへの不安もあるのだろう。
「しかし我々がグランバニアに戻っている間に天空城に動かれたのでは、もうルーラで戻ってくるのは難しそうですね」
ピエールがそう言って唸る前で、リュカもまた小さく唸り声を上げる。視線を落とした先には、自身が手にするドラゴンの杖の桃色の宝玉がある。竜の形を模したこの杖には、マスタードラゴンの力の一部が込められているという。先ほど、リュカが試しに桃色の宝玉に向かって念じた際には、寝かけていたマスタードラゴンがリュカの念に応じるように目を覚ました。この杖を通じて、リュカと竜の神は確実に繋がっているのだ。
ルーラの呪文で大事なことは、目的地をいかに具体的に頭の中に描けるかだ。常に場所を移動してしまう天空城の位置を定めるのは困難を極めるが、発つ場所と着く場所とで交信できる状況があることはむしろルーラの呪文を発動するのに適しているのだとリュカは考える。
「多分、大丈夫だと思う。この杖でプサン……じゃなくてマスタードラゴンに話しかければ、この天空城の位置もきっと分かるよ」
「お父さん、そんなことができるの?」
「うん、分からないけど、さっき試しにこの杖に念じてみたら反応してくれたから、どうにかなると思うよ」
「……まあ、確かなことはよく分かりませんが、リュカ王がそう仰るのならどうにかなるでしょう」
「別によう、どうにもならなくたって、いざとなったらさっき竜の神さんからもらったベルってやつを鳴らして呼べばいいじゃねぇか。そうしたらこの城まで連れてってくれるんだろ」
それまで皆の様子を見ながら大人しく話を聞いていたアンクルが、腕くみをしたまま気楽な様子で口を挟む。彼のその言葉に、考えが凝り固まっていた頭を解されるようにリュカたちはぽかんと口を開けてアンクルを見る。
「あっ、そうだよ! マスタードラゴンにグランバニアまで来てもらったいいよ! 国のみんなも竜の神様なんて見たら、びっくりするだろうね~」
「そんな使い方……バチが当たらないのかしら」
「リュカ殿にそのベルを渡したのですから、それはリュカ殿が自由に使うことができるわけです。使い方に関して、何も制限など受けていませんから大丈夫でしょう」
ポピーの心配を宥めるピエールだが、その言葉の端々に竜の神を神とも思っていないような気軽さが感じられた。彼の中にもまた期待していた神への失望があり、そのために自ずと不遜とも思えるような態度が出てしまうのだった。
リュカたちの会話の一部始終を近くで聞いていた天空人の兵士二人は、ちらちらと眠るマスタードラゴンを見ながらもリュカたちの意志に同意を示した。竜神自身がリュカに直接手渡した天空のベルであり、リュカたちが危険を掻い潜り、生死の危機に遭いながらも手にしたドラゴンの杖であり、神自らが生み出したそれらのものに対して天空人たちは口を出す術を持たない。その使用に関しては、リュカたちの一存にあるのだと、兵士らはただマスタードラゴンの怒りに触れないようにと身を震わせながらもリュカたちの話に同意を示す。
「天空城を動かすということですが、どういう航路を取るつもりですか」
問題は解決したと言うように、リュカはいつも通りの様子で天空人の兵士に話しかける。
「先ずは人間たちが多く住む場所を巡ることを想定しています。ここより東に砂漠の国があるようなのでそこへ向かい、その後は南下してもう一つの国へ……」
「テルパドールとラインハット……二つの国を巡るのに二月はかかるかな」
「途中、嵐に巻き込まれたりすればもっとかかるかも知れません。その間、我々はグランバニアで英気を養うなり、情報を精査するなりした方が良いでしょう」
ピエールの言葉自体は冷静なものだが、その実彼は疲れた身体を休めるのに国に戻りたいと思う本心もあった。それは他の仲間たちも同様だった。空に浮上した天空城は安全で、そこでも十分に身体を休めることはできるが、あくまでもこの場所は天空人が暮らす場所であり、人間や魔物であるリュカたちがのびのびと身体を休められる場所ではない。第一、彼らが本能的に欲している食物が圧倒的に不足していることで、リュカたちの疲れが完全に癒されることはないと感じてしまう。
リュカたちが一度グランバニアに戻ることを決めると、天空人の兵士らは玉座の間からリュカたちを見送った。リュカたちが立ち去る気配を感じたのかどうか、玉座に眠るマスタードラゴンが一度大きく鼻を鳴らした。主の立てる大きな音に身体をびくつかせた天空人の兵士らとは対照的に、リュカは依然として眠る竜神の鼾に苦笑いしつつ、子供と仲間たちと天空城を後にした。
ルーラの呪文は非常に便利だが、旅をして徐々に変わる景色を見ずに唐突にその場所へたどり着くため、郷愁を誘う暇もないような情緒に欠ける呪文だとリュカは感じている。年月を数えればおよそ半年ぶりのグランバニア帰還になるというのに、懐かしさを感じるよりも、夢でも見ているのではないかと思うような非現実の只中に放り込まれてしまうのだ。
深い森の中にあるグランバニアの城をしばし見上げる。森から生じる湿気の多い空気を肌に感じる。蒸し暑い空気の中にも、近くを流れる小川の清涼さを感じ取る。森の中に棲息する派手な鳥たちのけたたましい鳴き声を聞く。グランバニアと言う国を外の景色に十分感じてから、リュカたちは揃って城門をくぐって行った。
グランバニアは朝を迎えて少し経った頃だった。頑強な建物の中に入っている城下町では国民が一日の始まりを迎えたところで、まだ活気づくには時間がかかる。その様子を城門を入った奥に感じながらも、リュカたちは国の兵士らと短い挨拶だけを交わし、玉座の間へと向かった。リュカの後ろにはティミーとポピー、その後ろにはピエールとサーラが続く。他の魔物の仲間たちは国王代理への報告などと言う面倒事には付き合わないと言うように、勝手知ったる魔物たちの過ごす大広間へ行っていた。
玉座の間に通じる扉を番兵が二人で開け、リュカたちが姿を現せば、玉座の間では低いどよめきが起こった。約半年ぶりの国王の帰還に、近衛兵の表情も思わず緩む。玉座に着くオジロンも、オジロンと話をしていたサンチョも、揃って円らな目をぱちくりと丸くしている。
「ただいま戻りました」
「いつもいつも突然現れるものだから、どうにも心臓に良くない」
「先に手紙か何かで知らせた方が良かったですか?」
「いや、リュカ王には便利な移動呪文があるから、その必要もないのだろうが……いやあ、心臓に悪い。寿命が何年か縮んだ気がするわい」
「よくぞご無事でお戻りになりました。今回はなかなか長い旅となりましたな」
そう言うサンチョの白髪がまた増えているような気もするが、リュカは今は彼の変化を見つけないように努めた。今はまだ感傷に浸る時ではない。
リュカたちは手短に、今回の旅のあらましをオジロンとサンチョに報告した。グランバニアを天空城で旅立った後、山奥の村に立ち寄り、サラボナを滅ぼしかねない化け物を討伐し、その後で神の力が封印されていると言われていたボブルの塔に入った。無事に神の力の封印は解いたものの、リュカたちが期待していた王妃と前王妃の救出に繋がるものは得られなかった。旅の経緯を筋道立てて話したのは主にピエールとサーラだ。
「ふむ。いつもながらにとんでもないことをしてきているな、リュカ王は」
「そうですね。僕もピエールとサーラさんが話していることをしてきたのかって思ったら、してない気がします」
「しかしその大層な杖は紛れもなく坊っちゃ……リュカ王が経験してきたことを証明していますからな」
サンチョの目が釘付けになっているのは、リュカが手にしているドラゴンの杖だった。オジロンの目もまた、眩しそうにドラゴンの杖に向けられている。玉座の間にいる近衛兵の視線も同様に、桃色の宝玉を胸に抱えるドラゴンの杖に集まっている。
「この杖には神様の力の一部が込められているそうです。勇者の支えとなるものだと、マスタードラゴンが言っていました」
「まさにリュカ王が持つにふさわしい杖だ。王者の貫禄も出てピッタリではないか」
「オジロンさんが持てば、オジロンさんに王者の貫禄が出ると思いますよ。持ってみます?」
リュカがそう言いながらドラゴンの杖を差し出すと、オジロンは頭を振りながらも興味深そうに竜を模した大層な杖を見る。興味津々な表情には子供らしさが浮かび、その顔つきは武闘好きの娘ドリスにも通じるように見えた。「持ってみるくらいは良いかのう」と誰に対する言い訳でもない独り言を呟き、オジロンは玉座を立ちリュカに歩み寄ると、差し出されたドラゴンの杖を両手で恭しく受け取った。
初め、オジロンは想定外の杖の軽さに目を見張り、右手で高々と杖を持ち上げたが、それはすぐに下ろされた。ドラゴンの杖の外見に異変はないが、オジロンにはその重さが嘘のように変わったのが嫌でも分かった。軽い檜の棒を持っていたつもりが、突然サンチョが扱うような重々しい斧にすり替わったかのように重量が変化したのだ。玉座前の床がめり込まんばかりに杖先が打ち付けられ、オジロンはその衝撃に思わず杖を手放してしまった。床を転がるドラゴンの杖は、檜の棒が転がるような高い音を響かせる。
「天空の剣同様、持つ者を選ぶのだな、この杖は」
「あっ! そう言えばボク、その杖を持ったことないよ。持ってみてもいい、お父さん?」
オジロンが顔をしかめながら痛めた手を振る前で、ティミーがぱっと顔を輝かせて床に転がったドラゴンの杖に手を伸ばす。ティミーは自身が勇者であり、天空の剣を唯一装備できる自分にはこの大層な杖が装備できるに違いないと言う驕りがあり、猛々しい竜を象る杖を単に装備してみたいという好奇心も強まった。床に転がった時にはカラカラと高い音を響かせていたが、ティミーが杖の中ほどを持って上げようとすれば、それは床と一体化したかのように動かない。床に両足を踏ん張り、顔を真っ赤にして杖を両手で引き上げようとしてもびくともしない。隣からポピーも手を出し、双子が一緒になって床に横たわる杖を持ち上げようとするが、やはり動かない。
「リュカ王にのみ装備することのできる杖なのでしょう。勇者を守る者に……あの竜神はそう言っていましたね」
サーラが話す声を聞きながら、リュカは双子が懸命に床から引き剥がそうとしているドラゴンの杖に手を伸ばす。リュカが杖を持てば、ドラゴンの杖はリュカの手に懐くかのようにその手に収まる。その様子を見て感じて、ティミーもポピーもこの杖は父だけが手にすることのできるものなのだと心の底から納得した。天空の剣が勇者を選ぶように、ドラゴンの杖は勇者の護り手を選んだのだ。
「我々の旅がまだ続く中、リュカ殿は心強い武器を得られたということでしょう。それくらいの助けがなくては、リュカ殿の苦労に比べて割に合いません」
「そうよ……そうよね。だって、お父さんはあの塔で……」
ピエールの言葉を受けてポピーの口からも思わず言葉が飛び出したが、その先は続かない。ポピーの沈黙に、ティミーもまた表情を失い俯く。二人が鮮明にその時の悲劇の光景を思い出す前に、リュカが口を開こうとした時、ほぼ同時に口を開いたのがオジロンだ。
「ところで先ほどの話の中に『魔界の門が開きつつある』と言っておったが、それは以前、リュカ王が旅してきたエルヘブンに関わることではないのか?」
リュカはこれまでの旅の過程を細かにオジロンやサンチョに話し伝えている。口頭での報告で伝え切れなかったり、後に思い出したことなどあれば、書面に残し伝えている。人の記憶と言うのは曖昧で確かなものではないために、共に旅に出ていた仲間たちとも話し、報告書をまとめているのだった。落ち着いて旅の記憶を掘り起こすことで、改めて考えさせられることもある。
以前、まだリュカが石の呪いから解き放たれて間もない頃に、彼は子供たちを連れ、仲間たちと共に母の故郷であるエルヘブンを訪れたことがあった。母は父と出会わなければ、エルヘブンの未来を背負って立つほどの優れた能力を持つ巫女だった。その力は魔界の門を封じるほどのもので、彼女の他にその力を持つ者はいないと、人里離れた場所にひっそりと暮らすエルヘブンの四人の長老である巫女たちがそう話していた。
その魔界の門が徐々に開きつつあるという。リュカはエルヘブンの四人の巫女たちが水晶玉の中に見せた景色を思い出す。ルドマンからありがたく貰った大きな船で、広い洞窟の中を進んだ。分かれ道の先に、仰々しい二本の石柱が建ち、その奥に大きな火台に守られる巨大な青白い扉があった。扉に鍵がかかっていたのか、リュカたちには扉を開くことはできなかったが、巫女たちが見せる水晶玉の景色はその扉をすり抜けたのだ。
しかしリュカたちが水晶玉の中に目にした景色は、滝のような大量の水が上から下へと流れ落ちる景色までだった。その景色が水晶玉の中に現れるや、巫女の力不足か水晶玉の中に映る景色の力か、景色は白い靄の中に隠されてしまいそれ以上を目にすることは叶わなかった。
「あの時と何か状況が変わっているのかも知れませんね。一度、確かめに行った方がいいかも知れません」
「海の洞窟内でしたら、魔法のじゅうたんを広げて進めるのではないでしょうか。わざわざ船を操縦して行くより断然安全に行けるかと思います」
エルヘブンを訪れた時にも、サーラとピエールは共に行動している。彼らもまたエルヘブンの北東に位置する海の洞窟の景色を思い出し、今すぐにでも旅立つかのように揃って発言する。
「半年もの間、城を空けていたのだ。リュカ王には二月ほどは国王の執務に就いてもらうぞ。旅から戻った休息ももちろんだが、国王として民の人心を確かに掴んでおかなくてはならんからな」
「ふ、二月ですか? でもそんな悠長なことは……」
「坊っちゃ……いえ、リュカ王。王子、王女のことも案じて差し上げて下さい」
サンチョの口調は思いの外厳しい。真剣な従者の表情に、返す言葉もなく両腕をだらりと下ろす。右手に掴むドラゴンの杖の先が床を突き、桃色の宝玉が床に当たる高い音が鳴った。
「お二人の表情、旅に出る前と比べてまるで変わっておられます……。私には無理をされておいでのように見受けられます」
「……そんなことないよ、サンチョ! せっかくここまで来たんだから、早くお母さんとおばあさまを助けてあげないと!」
「そうよ、サンチョ。私たち、そのためにこうして頑張ってるんだもの。ここで止まっちゃうのはもったいないって思うのだけど」
「ことを急いては仕損じると申します。このような時こそ、焦ってはならないのです」
「それに王子王女の元気な姿を民に見せると言うのも王族の責任というものだ。子供が健やかに育っている姿と言うのは、それだけで人々に未来を見せることができるのだ。大事な仕事なんだぞ」
まるで爺が孫に言い含めるように優しく、オジロンはティミーとポピーの顔を交互に見ながらそう告げる。そんなオジロンの顔つきを見ながら、リュカは山奥の村で再会したビアンカの父ダンカンの皺の深く刻まれた寂し気な笑顔を思い出す。本当ならば可愛い孫たちを手放すことなく、自らの手元に置いておきたいと思うに違いない。しかし孫たちは一つ所に留まることなど好まず、むしろいつでも外に羽ばたいていきたいのだと羽をばたつかせている。
ティミーもポピーも、紛れもなくリュカとビアンカの子供ではあるが、同時にオジロンやサンチョの孫のようなものでもあり、グランバニア国民にとっては国を代表する王子王女であり、この国の未来を背負って立っている二人だ。そして二人はもう、赤ん坊ではない。子供ではあるが、何もできない子供ではない。彼らは背伸びをしながらも、どうにか一人で立とうとしている。そんな二人をリュカは親だからと言って勝手に独占し、囲っておくことなどできないのだ。
「……分かりました。でもその間も僕は多分、色々な国に飛び回ると思いますが、それは許してもらえますか」
「それは国王としての仕事の一貫だろう?」
「当たり前じゃないですか」
「それならば私が反対することもできないだろう。リュカ王の仰せのままに」
「……止めて下さい、突然畏まるのは」
オジロンが頭髪の半分も白髪に染めたような頭をリュカに見せてお辞儀をするのを、リュカは困ったように笑って止めさせた。二月の間、このグランバニアに留まると決まれば、リュカたちの間の緊張感が一気に緩む。しばらくは先の見えないような外の旅に出ることはないのだと身体が感じ、リュカたちは一人残らず、その場に足が崩れそうになるのを感じていた。そんな安心感に包まれて初めて、半年ほどグランバニアから離れていたという現実に気付いたような気になったのだった。
Comment
bibi様。
いつも小説更新ありがとうございます。
暫くの間コメントしていなくてすみませんでした…、色々とありまして…体調を崩していまして…ようやくコメントできるようになりました。
今から小説upされたものを急いで読ませて頂きますね!
ドラゴンの杖に念じたら何かが起きる、お楽しみは後にとっておく…てリュカたち言われても、ぶっちゃけ何が起きるか分からないから使いにくそうですよね、だって全世界もろとも破滅させるパワーを持ったマスタードラゴンですから(笑み)
まるでドラゴンボールの破壊神ビルスのよう(笑い)
あらかじめ説明しておいた方がリュカたちも使いやすそうな気がしますが…ドラゴラムと同じ効果ですからリュカどちらにしても使いにくいかも…?
でも、父娘が龍になって炎を撒き散らし魔物を倒す光景は圧巻ですな!
ケアル 様
コメントをどうもありがとうございます。
体調を崩されていましたか。ご無理なさらず、ゆっくりとお過ごしくださいね。
ドラゴンの杖の効果・・・知らされずに使うには相当追い込まれた場面になるでしょうかね。
ドラゴンボールはジャンプで終わるまでは見ていたんですが、その後の展開はまるで知らないんですよね(汗) 破壊神ビルスというキャラクターがいるんですね。私の中では子供のブウで終わってまして・・・。
父娘が竜になって炎を吐き散らしたら、それだけで世界がヤバイことになりそうですね。